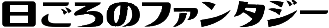お茶を初体験してみたら思っていたよりもスピリチュアルでした
自治体が主催する茶道教室にいってみました。近所に本格的な茶室のある施設があり、そこにお師匠さんたちが何人も集まって指導していただけるというとても豪華な内容です。
すべての動作に意味がある
- 歩き方とか
- お辞儀の仕方とか
- どちらの手で茶碗を持つのかとか
- どのタイミングで挨拶をするのかとか
- 畳の縁をどちらの足でまたぐのかとか
いちいちかなりこまかいんだなあと思いました。
そういうこまかさに気を付けるのとはまた別に、
- このタイミングでこういう挨拶をするのはこういう気持ちからそうすることになっていますとか
- ここでお茶碗のことをしげしげと見つめるのは、どんな面白い茶碗なのかなという純粋な興味を表すんですだとか
そんな感じでどうしてそういうお作法になっているのかを、つどつど解説していただけるので、とても自然に納得できました。
- なるほどそういう気持ちからこういう動作をするんだ
- こういう動作をするのはこんな気持ちだからなんだ
- 心と体は一体なんだ
ひとつひとつの動作にたいするきめこまやかな指導に注意を払いつつも、同時に行動できているというのがなんとも不思議です。
客観的にみるため、または衝動ではなく理性で行動するための知恵
決まったとおり行動することになっているからそんなことを考えたりできてしまうのかもしれません。
自分の欲望のまま行動しているとき、行動のもとになっている欲望そのものに気付かないとメッタヤタラに動き回ってしまいがちになりますが、その真逆の状態とでもいいましょうか、全てに理由を感じながら行動しつつその理由も行動も全て客観視できる、だからといって自分がなくなるわけではない、といった感じです。
ヴィパッサナー瞑想が近いかも。武道には間違いなく近い
スマナサーラ長老が本当の心を育てるのにおすすめといっているヴィパッサナー瞑想に近いかもしれません。そしてお師匠さんたちの立ち居振る舞いや、お茶の作法にのっとっていない日常の所作からしても、そういう姿勢で世界に相対しているんだということがわかりました。
夢中になっているけれども覚めてもいる。矛盾した自分を矛盾したまま見ることができている。
小さい頃空手をやっていたとき、稽古の最初と最後に短い黙想の時間がありました。その黙想しているときの状態のままずっと行動しているような感じの時間でした。
お茶は作法のかたまりではなく、知恵のかたまりでした
昔はお茶というのは単にお作法とかそういうもののことだとイメージとしていたんですがそれは勘違いでした。もっとずっと精神的な世界でした。
お茶の始まりが室町時代じゃなく、それよりも2000年ぐらい前だったら、生活の知恵に根ざしたもっと宗教的、または哲学的な何かになっていたかもしれません。そんなふうに連想してしまうぐらい新鮮な時間でした。