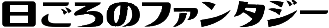クラシック音楽の入門にテレビ番組はかなりおすすめできる
ぼくはいまでこそ、クラシック音楽はいいなあ、とおもって好んで聴いていますが、始めからそうだったわけではありません。
たぶんきっかけが良かったんだとおもいます。
ぼくの場合はテレビ番組がきっかけでした。これは今振り返ってもラッキーでした。
テレビ番組は第一印象がよい
どこから入るか、入り口の違いによってその世界のイメージがまるで変わってしまいます。
入り口としてみた場合、テレビ番組はかなり品質がよく、情報の精度が高いうえに、そもそもエンターテイメントとして楽しめます。
特にマスタークラスのようなテイストの番組がおすすめです。
マスタークラスとは、当代一流の演奏家によるレッスンで、その人ならではの音楽、観点、言葉などを伝えてもらうのが目的のひとつです。
そしてマスタークラスですから生徒も尋常ではない水準で、のちの一流だったりします。
何も知らない門外漢がいきなり達人の秘伝を理解できるのか? と感じるひともいるかも知れませんが、ところがどっこい、人間が本来もっている感覚に直接訴えかけることを追いかけている一流のことばは、余計な知識の入っていないド素人にこそまじりけなしに純粋に響くのでご安心を。
ぼくがクラシック音楽と出会う前は、クラシックで知っている曲は、映画、テレビ、ラジオ、学校の授業で耳にしたことがあるものなら、聞いたことがあるとわかる程度でした。
つまりぼくには音楽と曲名が一致するクラシック曲はひとつもありませんでした…… いや、『運命』が「ダダダダーン」くらいは知っていました。
そんなぼくのクラシック音楽とのファースト・コンタクトは『ショパンを弾く』でした。
クラシック音楽入門は『ショパンを弾く』というテレビ番組だった
NHKの教養番組で、たぶん本放送の翌日午後くらいに再放送をしていたとおもいます。
ある午後たまたま一人で家にいたぼくはその再放送をみていっぺんにひき込まれました。
それまでクラシックとロックはあまり関係ないものだとおもっていました。
当時バンドでギターを弾いていたのでそんなふうにおもっていたわけですが、そもそも幼児のころのぼくは、音楽は女がやるもの、ピアノをならっている男子はオカマだ、などとおもっていたくらいです。
ぼくがバンドをやろうとおもったのは、ロックは怒りやら衝動やら不安やらがそのまま音にのって爆発してる、なんだかすごいことがおきている、これが音楽だったんだ、と衝撃をうけたからです。
そうして音楽に目覚めたものの、ぼくにとってクラシックは依然としてお稽古ごとであり、音楽というよりは儀式に近いものとしてイメージしていました。
だからその後もしばらくはクラシックに興味をもつことはありませんでした。
ロックバンドの曲をコピーしたりして、バンドで練習したりして、文化祭で演奏したりすると、その先にオリジナルの曲を作りたいという欲求がうまれてくるのは自然です。
ぼくが『ショパンを弾く』を偶然みたのは、ちょうど曲をつくるにはどうしたらいいのだろうとおもい始めたころでした。
講師はシプリアン・カツァリスさんというピアニストでした。
その曲の世界を熱くかたる先生は熱中のあまり立ったり座ったりしながら身振り手振りを交えつつ一番楽しそうでした。
生徒さんたちはお稽古ごとの世界からきているのであっけにとられていて、完全においていかれた格好になっていました(言葉の違いの問題かもしれません)。
もう一度みたいとおもって探してみたらシプリアン・カツァリスさんご本人が youtube にアップしてくれていました。
生徒さんがお稽古ごとの世界から音楽の世界につれていかれて、演奏がみるみるよくなっていくのがおもしろいですよ。
テレビ番組のおかげでしあわせなクラシック音楽入門ができた
ぼくはこの番組に出会えたおかげで、クラシックが儀式的なものではなく、芸術的なものだとわかりました。
作曲者の熱いおもいは音楽をとおしていまをいきる人にも伝わってきます。
過去の偉人ではなく、自分と同じように感情のある人間として生々しい存在が感じられたのです。
クラシックが「今ここでおきていること」としての音楽になった瞬間でした。