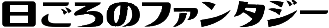文章のリズムが体感できる名文サンプル、書き写し中にあばれる君のラップがよぎってわかった共通点と表現の本質
「文章のリズム」とは何か?
それはビールでいう「のどごし」と同じです。
どちらをとっても明確に説明できる人はまず居ません。
たとえ明確に説明されたところでわかってない人がわかるようになるのかといえば、やっぱりよくわからないでしょう。
理屈ではなくて体感だからです。
こういうものは実例で体感するのがいちばんです。
そこで今回サンプルにとりあげるのは、中島敦の『名人伝』です。
『名人伝』はさすがの名文で、もともと「文章のリズム」というものを気にしていたわけではないのに、たまたまこれを読んでみたら「文章のリズム」がどういうものか、自分の体感でばっちりわかりました。
しかもラッキーなことに文章のリズムとラップとの共通部分もわかるというオマケ付きです。
(ここから先はかなり端折ったあらすじを書いている部分があるので、未読のかたは、まず純粋に作品を味わわれることをおすすめします。原稿用紙たった15枚分の短編です。→ 青空文庫 中島敦『名人伝』)
名文サンプル 中島敦『名人伝』
『名人伝』は、ものすごくざっくりいうと、紀昌という男が天下第一の弓の名人になろうと志をたてるところから、師をたずねて修行をつみ、やがて名人になって、彼がそのときたどりついた境地と、それについて周囲がみせる反応までを描いた物語です。
これから引用する部分は二人目の師との出会いのシーンですが、そこまでの紆余曲折がわかっていてこそ響くものになっているので、簡単に紹介します。
有名な弓の名人である一人目の師に教えをうけて5年以上にわたって修練を重ねた紀昌は、師に並ぶほどの実力に達します。
ここで紀昌は自分が天下第一の名人となるために師を殺そうとして失敗します。
このとき師は、再びこのような危険なたくらみを抱かれてはたまらないと考えて、紀昌にこう伝えます。
はるか西方の険しい山のいただきにものすごい大家がいる。その人の前ではわれわれの技のごときはほとんど児戯にひとしい。さらにこの道を極めたいなら、師とたのむべきはその人しかいない。
もうほとんど天下第一の名人の域に達していたと思っていたので、紀昌は師の言葉に大きなショックとあせりを感じ、すぐに西にむかって旅立ちます。
ともかく腕比べしたいとの一念から2ヶ月にわたる険しい行程を突破して、ようやく目指す山のいただきにたどり着きます。
そこで紀昌を迎えたのは、仙人のような風体をした、ごく柔和そうな年寄りでした。
紀昌は自分の技をみてもらいたいむねを伝えるが早いか、相手の反応を待つことなくいきなりデモンストレーションを開始し、たまたま上空を渡っていた鳥の群れを狙い、たった一矢で五羽をも射落としてみせます。
これに対する老師の反応から引用を始めるので、名文の凄みをご堪能ください。
一通り出来るようじゃな、と老人が穏かな微笑を含んで言う。だが、それは所詮(しょせん)射之射(しゃのしゃ)というもの、好漢いまだ不射之射(ふしゃのしゃ)を知らぬと見える。
ムッとした紀昌を導いて、老隠者は、そこから二百歩ばかり離れた絶壁の上まで連れて来る。脚下は文字通りの屏風のごとき壁立千仭(へきりつせんじん)、遥か真下に糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけでたちまち眩暈(めまい)を感ずるほどの高さである。その断崖から半ば宙に乗出した危石の上につかつかと老人は駈上り、振返って紀昌に言う。どうじゃ。この石の上で先刻の業(わざ)を今一度見せてくれぬか。今更(いまさら)引込(ひっこみ)もならぬ。老人と入代り(いれかわり)に紀昌がその石を履んだ時、石は微かにグラリと揺らいだ。強いて気を励まして矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。その行方を目で追うた時、覚えず紀昌は石上に伏した。
文章にリズムを感じて、あばれる君のラップが思い出された瞬間
デモンストレーション直後の、おそらくはドヤ顔をしていたであろう紀昌に対して、老師はまず一発カマします。
そして平常ではいられなくなった紀昌をものすごい高さの断崖絶壁まで連れてきます。
この部分は老師のセリフと、それに続く情景の描写だけです。
にもかかわらず、老師の発するオーラの異次元感、紀昌の心の動揺、高所恐怖が誘発されるときのあの感覚、これらがまるで自分に起きていることのようにつぎつぎと湧き上がってきます。
その高い断崖から半分宙に突き出している石に老師が何の気後れもなく駆け上がった瞬間、物語の現場で起きていることと、文を読み進めることとが完全に一致し、同じ時間で進行し始めます。
自分が読み進めるテンポで物語が進んでいるのか、物語が進むテンポで読まされているのかよくわからなくなってしまうほどのシンクロ率です。
ここではまったく読み返す必要のない、一読するだけで完全に意味がつかめるシンプルな記述が続きます。
それを一直線にたどっていってついに紀昌が石上に伏したとき、読んでいるだけのぼくも高いところでほんとはこわいのを我慢して動くときのからだになっていました。
窓ふきのバイトをしていたことがあるのでこの感覚はよくわかります。
この作者が高所作業の経験なしにこれを書いているとしたら、おそろしい文章力です。ほとんど超能力者です。
文章にリズムがあるのは短文だからとは限らない
この部分は確かにテンポ良く進んでいくリズム感がありますが、その推進力は文の短さというよりもむしろ形式から生じています。
「今更引込もならぬ。」の短い文でリズムに弾みをつけたあとに「Aの状態にあるとき、Bが起きた」という形式が3回畳みかけられます。
「老人と入代りに紀昌がその石を履んだ時、石は微かにグラリと揺らいだ。」
「強いて気を励まして矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。」
「その行方を目で追うた時、覚えず紀昌は石上に伏した。」
これが見事に3つとも同じ形式なので、読むほうは文章構造に神経を使うことなく、全リソースを物語中の出来事に集中できます。
しかも形式が同じであるうえにパーツごとにほぼ韻を踏んでいるので、ほとんどラップのようです。
こうなるとあまりにも読むのが楽なので、文を読んでいる感覚というよりも、自分の眼前に繰り広げられている光景そのもののように感じるわけです。
光景そのものどころか、「微かにグラリと揺らいだ」なんて石をふんだ本人にしかわからない感覚です。
これで一気に物語中の出来事が読者自身に現在進行形で起こっていることになります。
ところで、こういうことがわかったのはこの文章をじっくり分析したおかげ、というわけではありません。
あばれる君のおかげです。
『名人伝』とラップの共通点
ぼくは文章を書き写すとき、まずある程度まとまった量の文を暗唱できるようにしてから、覚えた文を書き出すことにしています。
暗唱しようとしてブツブツと文をとなえているとき、なぜか、あばれる君が街頭でラッパーにからまれるドッキリを思い出しました。
以前に経験があったからといって、なんの準備もしていないところに、しかも身の危険を感じる状況なのに、いきなりここまでできるのはかなりすごいと思います。
単純にことばを並べるだけでなく、きっちり韻を踏んでいるあたり、本物を感じました。
即興でこういうことができるということは、その習熟度はほとんど習性になっているといってもいいほどのレベルだということです。
中島敦が『名人伝』を即興的に書いたかどうかはわかりません。
しかし、まったなしで今ここに起きていることを表現しようとして、ラップと共通するやり方、つまり韻を踏みながら同じ構造の文をたたみかける方法にたどり着いたことは間違いありません。
だから暗唱しているときにあばれる君のドッキリを思い出したりするわけです。
共通点から垣間見えた表現の本質
文章もラップも人間の感覚を媒介に個人的な真実をコミュニケートするものである以上、形式よりも先に自分をとりまく世界全体を素直に感じることが第一です。
これがあって初めて、ほかの人が同感できるような最適な形式を工夫できるようになります。
ぼくらが誰かの作品に触れるとき、こうして練り上げられた形式をとおして、作者の感じている世界が自分のことのように再現されるのを無意識に期待しています。
簡単にいうと、未知の世界を体験してみたい、ということです。
作品をとおして体験する未知の世界の鮮やかさは、作者の感覚をどれだけ体感できるかによっています。
もちろん感覚が再現されるだけの形式の巧みさも重要ですし、作品を享受するひとのそれまでの経験の蓄積にも左右される部分はあります。
でも本物なら誰でもわかります。
小さな子どもでもわかります。
むしろ子どものほうがまっすぐ本質をつかみます。
文章を書き写すとき、それは完全に個人的な体験ですが、もとの文章を書いた作家の本質と同期しようとする体験ともいえます。
あれこれ分析してわかったような気になるよりもよっぽど得るものが大きいです。